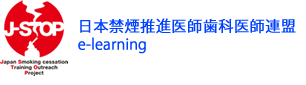(3)精神疾患と禁煙、各論
1)統合失調症
慢性期にある統合失調症患者は前述の図表14「精神疾患患者の禁煙支援の実際」に従って治療すると比較的楽に禁煙できる。こまめなフォローがポイントとなる。
喫煙する統合失調症患者が急性症状で入院して高容量の薬物投与を受けた時の不穏状態は、ニコチン離脱症状や禁煙による投与薬剤の過度の血中濃度上昇による症状である可能性もあり、鑑別を要する。
精神疾患は再喫煙のリスクを増加するがニコチンパッチによる治療は統合失調症の陰性症状とうつ症状を改善することを示唆する報告がある。
ニコチンが抗精神病薬の副作用である錐体外路症状を軽減することを過剰評価する精神科医療従事者もいるが、統合失調症患者においても禁煙のメリットのほうが大きい。
喫煙すると薬によっては肝臓での抗精神病薬の代謝が促進されより多くの抗精神病薬が必要となり、その結果、逆に錐体外路症状を含めた副作用が出やすくなる可能性がある。また、最近の非定型抗精神病薬は錐体外路症状が少ないことが特徴の一つである。したがって、錐体外路症状軽減のために喫煙を継続させるというのは誤った考え方である。
2)うつ病
喫煙者ではうつ病の生涯罹患率は非喫煙者の2倍以上であり、逆にうつ病患者はニコチン依存症になりやすい、抑うつの重症度と喫煙との間には相関関係がある、禁煙初期の抑うつ症状は再喫煙率を高める、とされている。その理由としては、うつ病患者はニコチンによる抗うつ効果を経験しているので抑うつ症状があると喫煙への欲求が強くなること、禁煙でより多くの離脱症状や以前よりも強い抑うつ症状を経験すること、喫煙は身体疾患を惹起しやすいがうつ病ではその疾患特性により身体疾患を合併しやすく、身体疾患の存在がうつ病を悪化させるという悪循環に陥りやすくすることが考えられる。
うつ病の既往がある場合には、禁煙をきっかけにうつ病の再燃をきたしやすくなるので注意が必要である。禁煙治療プログラムに参加したうつ病の寛解患者を対象に、禁煙後の再燃を調べた研究によると、禁煙者では喫煙継続者に比べてうつ病の再燃が約7倍と高く、その危険性は少なくとも6ヵ月まで続いたと報告されている(文献1)。
以上から、うつ病患者の禁煙は精神科主治医との連携がより重要であり,抑うつ症状の変化には最大の注意を払わなければならないことが理解できよう。
うつ病患者でうつ症状がある場合、第一選択薬の禁煙補助薬の他にノルトリプチリンや認知行動療法を考慮するとよい。ノルトリプチリンはAPAガイドラインでもUSガイドラインでも禁煙補助剤の第2選択薬に挙げられており、うつの有無にかかわらず禁煙治療に有効とされる。なお、うつ病の既往のある喫煙患者において、ブプロピオン(日本では発売されていないが、APAガイドラインでは第一選択薬の一つ)とノルトリプチリンvsプラシーボを比較したメタ解析では、長期禁煙率のオッズ比は3.42(95%信頼区間1.70−6.84)、禁煙率は29.9%(95%信頼区間17.5%−46.1%)であった。これらの研究ではすべての患者に集中的な心理社会的介入が行われていた。
引用文献
1) Glassman AH, Covey LS, Stetner F, Rivelli S. Smoking cessation and the course of major depression: a
follow-up study. Lancet. 2001; 357(9272): 1929-32.