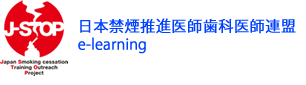5)「家族・周囲のサポート(含心理社会的治療)」
家族には喫煙がニコチン依存症という病気であることを理解してもらい、精神疾患患者の禁煙をあたたかくサポートしてもらうとよい。家族に喫煙者がいると再喫煙しやすくなるため、家族にも一緒に禁煙を勧め、それができない場合には喫煙は外で患者から見えないようにしてもらう。再喫煙時は受診するように本人や家族に話しておくことが推奨される。1本吸ってしまった時に本人を責めるような言動は慎んでもらう、けんかをしないというようなことが大事である。
医師以外の医療従事者のサポートも得られると効果は大きく、心理社会的支援の量が多いほど禁煙率は高いとされる。
米国精神医学会(以後APA)の「物質使用障害患者の治療、第2版」(以後APAガイドライン)によると、国立がん研究所が推奨するプロトコールを使った医師からの簡単な助言は、禁煙率を2倍(約5%から10%に)に高める。医師以外の職種の助言も有効で、多職種による助言はさらに効果的である。このように精神科医だけではなく、看護師やソーシャルワーカーなど他の精神科医療従事者が直接「タバコをやめなさい」「タバコをやめることを強くお勧めします」というはっきりとした助言をすることは、禁煙治療の準備と動機を増強する必須の治療ステップである。
認知行動療法は禁煙治療においても効果的で、薬物療法と併用することにより、さらに禁煙率を高める。特にうつ病や薬物依存症で有効とされる。
6)「環境」・・・敷地内禁煙は広義の禁煙治療
精神疾患患者は環境に左右されやすい。周囲に喫煙者がいたり、喫煙できる環境であった場合、タバコを吸いたくなるのは非精神疾患患者以上である。逆に禁煙しやすい環境があれば意外と楽に禁煙できる。改正健康増進法により精神科病院も原則敷地内禁煙となったが、そこでは大きな問題なく多くの患者が禁煙を達成している。沖縄県のある単科精神科病院では敷地内禁煙前は入院患者の喫煙率が6割であったが、敷地内禁煙にしたところゼロになった。まさに敷地内禁煙は入院患者にとって個々の禁煙治療を上回る広義の禁煙治療といえよう。