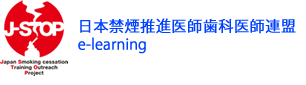3.禁煙治療の方法と実際
(1) 禁煙の動機付け
すべての精神疾患患者に喫煙の有無を聞き、喫煙者にはあらゆる機会を捉えて「はっきりと」「なぜ禁煙すべきか」「禁煙がいかに大切か」について個人に合わせたメッセージを用いて、「繰り返し」禁煙を促す。特に身体疾患合併時や入院時は禁煙のいいチャンスである。以下に具体的に解説する。
1)「はっきりと」「繰り返し」禁煙するように言う
慢性精神疾患患者には認知機能障害として注意の障害・記憶の体制化の障害・情報の文脈 的処理の障害がみられる。このため、あいまいな表現ではなく、わかりやすく・繰り返し・はっきり言うことが必要である。
【アドバイスの例】
・ 喫煙はニコチン依存症という病気です。禁煙が必要です(タバコをやめることを強くお勧めします)。今は禁煙のためのいいお薬があって楽にやめられますよ。
2)「なぜ禁煙すべきか」「禁煙がいかに大切か」を機会を捉えて言う
精神疾患患者が喫煙するとニコチン依存症になりやすく、ニコチン依存症になると治療コンプライアンスが悪くなったり、日常生活機能の低下が見られたり、QOLが低くなったりする。タバコを吸わないと離脱症状が出て精神状態にも影響がでるために吸わずにはいられず、1日喫煙本数も多くなる。また、身体合併症を起こしやすく、精神疾患患者では虚血性心疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、糖尿病や高脂血症、呼吸器感染症などが多いが、これには喫煙の影響もある。
精神疾患患者はきっかけがないとなかなか禁煙に踏み切れず、身体疾患の合併症や入院を禁煙のチャンスと捉えて禁煙を勧める。
【アドバイスの例】
・ 咳が出て苦しそうですね。これは○○さんが言っていた風邪ではなく、COPD慢性閉塞性肺疾患というタバコ病です。一番の治療は禁煙です。タバコをやめることが必要です。
・ 今回の入院をきっかけにタバコをやめましょう。入院中はスタッフみんなが○○さんの禁煙を応援しますから、外来で治療するよりも楽ですよ。禁煙して逆にいらいらしなくなった、不安が少なくなったという人は多いですよ。